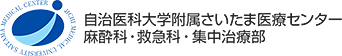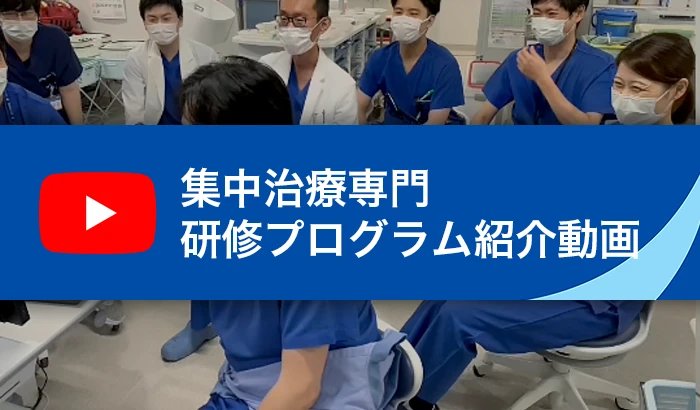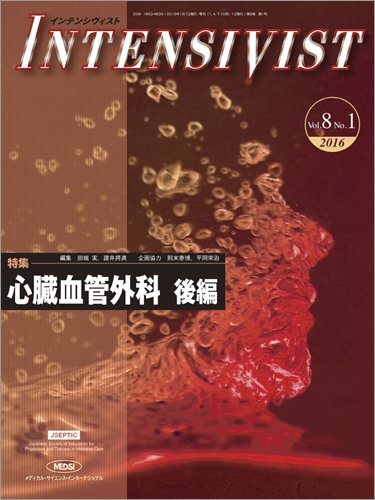はじめに
『ここでしかできない挑戦がある~急性期医療の最前線から、命を守り、未来を変える人材を育成する~』
私たち自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部は、上記のMissionを掲げ、急性期に幅広く活躍できる人材を育成することを目標にしています。研修を受ける本人と相談しながらテーラーメイドの研修プログラムを作成し、経験豊富な指導医のもと、自施設だけでなく自治医科大学附属病院含めた国内外の施設で多様かつ豊富な症例を経験し、最高のトレーニングが受けられる環境を提供します。
その過程で、臨床研究データや生理・薬理に基づく説得力のあるディスカッションができ、意思決定ができるようになることを最大の目標にする一方、重症患者を救命するための実践的な技術や判断力も養います。研修終了後には、真の実力を備えた急性期重症患者総合医になることができるでしょう。
今までの専従集中治療医のバックグラウンドは、麻酔科、救急科、総合内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、血液内科、外科、心療内科と多彩で、各専門バックグラウンドの英知を結集して、診療ばかりでなく教育および研究にも力を注いでいます。
当施設研修の特徴
当施設は、国内でも指折りの心臓血管外科センターとして年間500件以上の開心術を行っています。このような心臓血管外科周術期症例は、集中治療部医師がICU入室から退室まで術前・術後を、多様な循環器系疾患を学ぶことが可能です。また、気管切開、各種ドレーン挿入、ECMOの導入・管理を含め、ICUで必要なほとんどの侵襲的手技を我々のチームが行うので、十分な経験を積むことができるでしょう。
その他、ICUに入室する患者さんの約2割は内科的な疾患で、敗血症を筆頭に造血幹細胞移植後の多臓器不全などの多彩な病態を経験することが可能です。現在のメンバーのバックグラウンドは、麻酔、救急、総合内科、循環器科、血液科、外科など多様で、相互に不得意な分野を補いながら急性期総合医療チームとしての機能を最大限に高めています。
2024年からは方山部長が就任し、人工呼吸管理に関する様々な臨床・教育・研究への取り組みを加速化させています。安全な人工呼吸管理について、自発呼吸の質を評価する手法、様々なイメージングモダリティ(EITや4D-CTなど)の解析など、様々な呼吸管理を一から学ぶことが可能となりました。臨床のみならず、研究面でも世界的に学ぶことができることが、新たな強みとなっています。
また、2016年4月1日には埼玉県で8番目の救命救急センターを開設し、3次救急症例も経験することができる体制となりました。ICU・CCU・EICUは30床と非常に多く、多くの症例を経験できる体制です
大学附属病院でありながら臨床が重視され、各科間の協力体制も良好です。また、M&M(morbidity & mortality)カンファレンス、RST(respiratory support team)、RRS(rapid response system)など、院内横断的に多科・多職種が関わる活動が盛んで、我々のメンバーがその中心的な役割を果たしています。
研修の過程で、希望者には単施設・多施設臨床研究や基礎研究を計画・実践し、成果を国際学会や国際雑誌で発表する能力を養い、学位取得をサポートします。また、国内外の他施設での研修を積極的に推奨しています。
研修プログラム
麻酔科コース
主として当センター手術室における研修を中心に、他施設での研修を含めた各科麻酔の研修、当センター集中治療部での研修を行い、最初に麻酔科専門医の取得をめざします。その後に集中治療専門医を目指します。
内科系コース
当センター内科系シニアレジデントプログラムに従い、総合内科専門医の取得をめざします。その後に集中治療を目指します。
救急科コース
救急科としての勤務や研修を継続しながら、集中治療研修(希望に応じて麻酔研修も)が可能なプログラムです。 3-6ヶ月の救急科勤務を行いながら、集中治療(麻酔)を学ぶことが可能です。
集中治療部/血液内科ローテーションプログラム
神田善伸教授を中心とする自治医科大学血液科グループは、造血幹細胞移植数は附属病院とさいたま医療センターをあわせて年間130件を超える国内最大級の移植施設となっています。一方で、本邦では集中治療医の絶対数も少なく、造血幹細胞移植を行っている施設に集中治療部がなく、主治医が集中管理を行っている施設も少なからずあると考えられます。そこで、当院血液内科の御協力のもと、血液内科と集中治療部をローテーションできるプログラムを用意いたしました。移植件数、臨床研究共に国内トップクラスの血液内科と最先端のEBMに基づいたIntensivistを有する当集中治療部で研修を受けることができます。研修期間・待遇に関しては柔軟に対応可能ですので、個々の希望に応じて調整いたします。
基礎専門医資格部分他科研修コース
集中治療専門医は指定された学会の専門医資格が必須となります。そのため、主として当センターにおいて、内科系、外科系の各科、小児科などの各科専門医研修を行い、希望の1階部分の専門医資格を得た上で集中治療専門医を目指すコースです。各専門診療科と協力しながら最適な研修プログラムを提供します。
短期研修・見学
1〜6ヶ月程度の他施設からの短期研修や、見学を随時受け入れておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、当センター内での他科ローテート研修も積極的に奨励しています。
研修の実際
AM 8:15 モーニングレポート:前夜当直医からの簡単な申し送り。当日の入退室の申し送りと、様々な教育イベントなどの共有を行います。
AM9:00-12:00 モーニングラウンド:フェロー含めた担当医がプレゼンテーションを行い、病態生理、解剖学、薬理学、臨床研究データなど多角的に患者の病態を評価し、看護師含めた多職種と十分なディスカッションを行い、治療方針を決定します。
その後、アテンディングによるベッドサイド・ティーチングにより、”生きた知識”を身につけることができます。
カンファレンス
指導医によるレクチャー:週1回
内科医や麻酔科医など様々な背景を有する、当センターならではの「活きたレクチャー」を受けることができます。
ジャーナルクラブ:毎週火曜日
リサーチ・カンファレンス:月1~2回
麻酔科・ICUグランドラウンド:月1回
M&Mカンファレンス:月1回+α
これらの講義は、すべて院内のサーバーに保管されており、オフジョブの時間帯でも動画で学べるようなシステムを構築しています。
これにより、働き方改革に合わせた有効な時間の使い方を提供することが可能となりました。
推薦図書
「世界標準の集中治療を誰にでもわかりやすく」をコンセプトに、若手医師の育成や情報交換を目的として発足した「日本集中治療教育研究会」(Japanese Society of Education for Physicians and Trainees in Intensive Care=JSEPTIC)の活動をベースに、年4回発行。
集中治療部部長の讃井教授が著者・責任編集者として多くの巻の発行に関わっています。